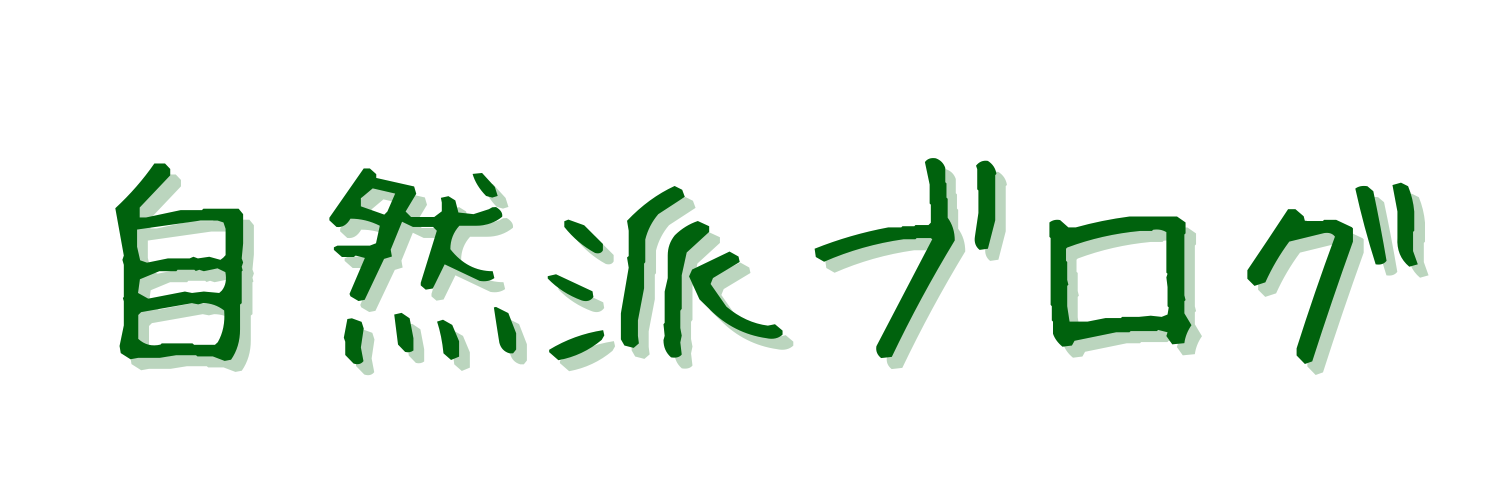醬油は日本人の食卓に無くてはならない物の1つですよね。

私も醬油は大好きな調味料の1つです
本当においしい醤油はそのままご飯にかけて食べても美味しく幸せな気持ちになれます。
とはいえ、スーパーには様々な醤油が並んでいて、本当に質の良い醤油を選ぶのは難しいですよね。

質の良い醤油の選び方がわからない…
そこでこの記事では、本物の醤油の見分け方のコツをご紹介します。
- 本物の醤油の見分け方のコツ
- 知っておきたい醤油の基本知識
- 醤油の種類と料理との相性
- おすすめの醤油
ちなみに、おすすめの醤油はこちらの商品です。

この商品については、後半で詳しく説明しています!
本物の醤油の見分け方を知って、健康的な食生活だけでなく、今の料理をワンランクアップさせたい方の参考になれば嬉しいです。

本題に入る前に、知らないと損なとってもオトク情報を1つ共有します!
無農薬野菜のミレーのお試しセットのレビューは、以下の記事にまとめているのでぜひ参考にしてください。

それでは見ていきましょう!
※「先に、おすすめの醤油について詳しく知りたい」という人は、〚こちら〛をクリックすると該当箇所に飛べます!
【結論】本物の醤油の見分け方は?
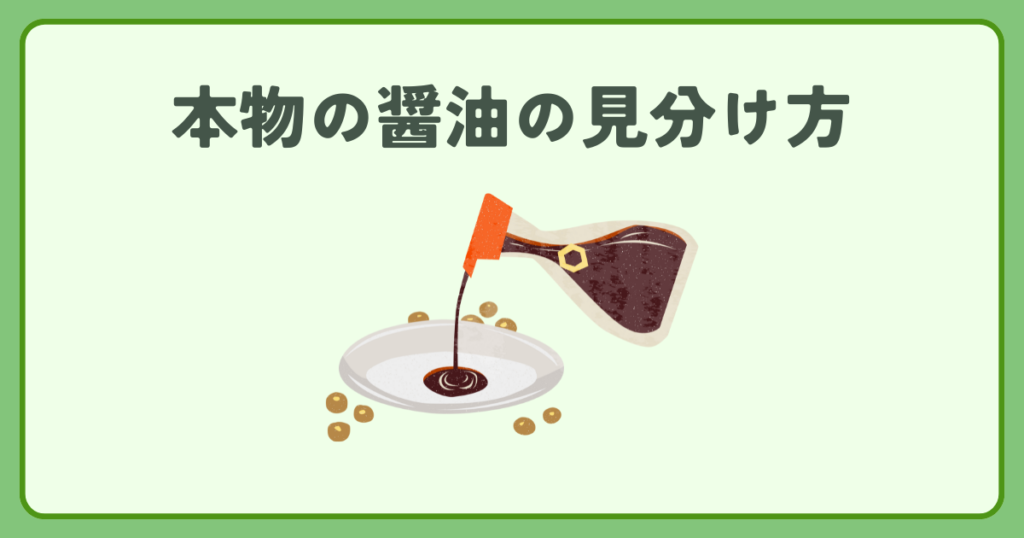
結論から言うと、
名称に書いてある原材料と製造方法で確認します。
①原材料が、大豆、小麦、食塩
かつ
②製造方法が、本醸造または、天然醸造
が本来の本物の醤油です。
なぜ本来と言ったかというと、
実は悲しい事に今の日本の規定では「大豆、小麦、食塩」以外に、国が指定する添加物が使われていたり、製法も指定の添加物で味を調えたり、発酵を促進させたりした物も醤油と呼んで良いことになっています。
しかし、醤油は発酵食品です。
本来の醤油のパワーはやはり添加物で補うと減ってしまいます。
そこで今回は、国が認めた添加物入りの醤油も含めて本物と呼ぶのではなく、「大豆、小麦、食塩」だけで作られ、作り方も本来の製法できちんと発酵させた作り方の醤油を本物と位置づけて見分け方の紹介をしていきます。
国は、「大豆、小麦、食塩」以外にも以下の原材料を使用していても醤油と言って良いと規定しています。
国が定める原材料

国は、「大豆、小麦、食塩」以外にも、以下の原材料を使用している場合でも「醤油」として認めています。
次に挙げるもの以外は使用しないことが規定されています。
- 大豆
- 小麦、大麦及び裸麦
- 米
- はと麦
- 小麦グルテン
- 食塩
- アミノ酸液、酵素分解調味液及び発酵調味料
- 砂糖類
- アルコール、焼酎及び清酒
- 米発酵調味料、醸造酢、みりん及びみりん風調味料
このリスト内の材料のみを使っていれば、醤油として認められるというルールです。
【解説】本物の醤油の見分け方
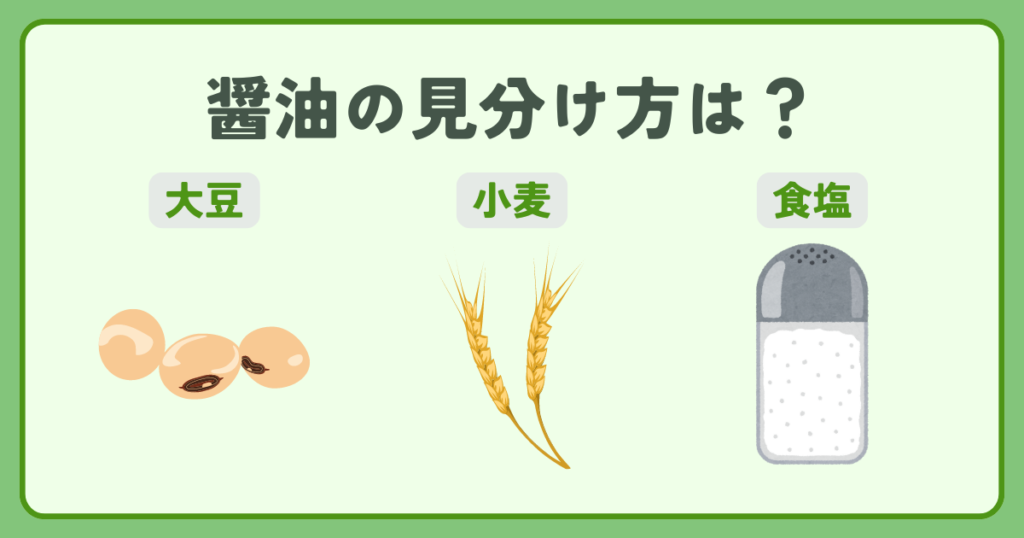
それでは、本物の醤油の見分け方について詳しく解説していきます。

2つのポイントを確認してね!
原材料
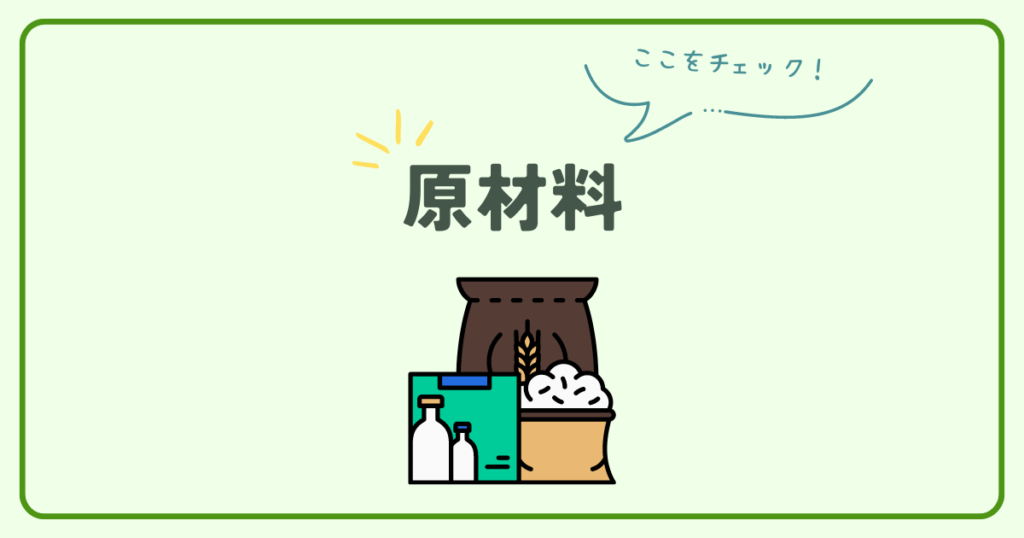
本物の醤油の1つ目のチェックポイントは、
原材料が「大豆、小麦、食塩」
有機大豆、有機小麦、海塩などの天然塩から作られているのが本物の醤油だと思います。
これら3つ原材料は、主に以下のような働きをします。
・醤油の味は、主に大豆のたんぱく質がうま味成分のアミノ酸に分解されて作られる
・香りは主に、小麦のでんぷんがブドウに分解されてできる
・塩は、雑菌から守り、麹菌、乳酸菌、酵母などの微生物の働きを調整する
これらが互いに作用し、じっくり時間をかけて発酵・熟成し醤油が誕生します。
大豆や小麦の質に関しては、日本の自給率は低く、大部分が輸入に依存しています。有機大豆や有機小麦の割合はさらに低いと考えてよいでしょう。
とはいえ国産有機がベストです。
大豆

大豆は、丸大豆と脱脂加工大豆どちらが良いのでしょうか?
醤油に使う大豆は、丸のまま使う丸大豆と、大豆から油分を抜いた脱脂加工大豆があります。
表示にも大豆、または脱脂加工大豆の表示があるので見分けられます。
実は国内の約80%は脱脂加工大豆が使われています。
脱脂加工大豆の醤油はコストも抑えることができ、生産効率も良く、油の酸化も心配なく大量生産に向いています。
ただ油を搾る過程でヘキサンという溶剤が使われていることや、大量の輸入大豆をまとめて絞るので大豆の安全性はわかりません。
丸大豆は、手間はかかりますが、ゆっくりと熟成させて作るので、まろやかな風味と深いコクが出てきます。
本物の醤油を求めるなら、
そのまま使っている大豆、できれば有機大豆の方が良いでしょう。
小麦

国は小麦以外にも、大麦、裸麦、米、ハト麦を使用しても良いと規定されています。
小麦や大豆が手に入りにくい時代や地域の特産として作られています。
また、小麦や大豆アレルギーの方は米醤油という物もあります。
これらは、無添加で本醸造(または天然醸造)であれば本物の醤油と言って良いと思います。
また、小麦グルテンについては、小麦からでんぷんや糖質を取り除き、残ったグルテニンとグリアジンという2つのたんぱく質です。
小麦グルテンを使った醤油はコスト削減や発酵効率が良くうまみもあります。
ただ、でんぷんや糖質を除いてあり、甘味はアミノ酸液などを加えて味を調えます。
添加物を加えてあるので、ここでは本物から省きます。
食塩

食塩は、やはり海水から天然に作られた海水塩が良いでしょう。
日本は戦後の政策により加工品のほとんどはミネラルが入っていない精製塩です。
古来からずっと取り入れていた海からのミネラルは意識しないとほとんど摂れていないのが、今日の食生活です。
醤油は日々に欠かせない調味料です。
ミネラルを摂るためにもぜひ、海水から作られた天然塩を使っている醤油をお勧めします。
表示には海水塩でも食塩とか塩などと書いてあったりします。
そこからは精製塩なのか天然塩なのかわかりませんが、天然塩の場合は、きっとラベルのどこかにそのアピールがあると思います。
天然塩についてはこちらにまとめているので良かったら参照にしてください。
製造方法

製造方法は、本醸造か天然醸造が本物の醤油です。
名称の所に書いてあります。
国が認めている製法は3つ「本醸造」「混合」「混合醸造」です。
大きな違いはアミノ酸液を入れているかどうかです。
本醸造
「本醸造」や「天然醸造」には、アミノ酸は入っていません。
伝統的な製造方法で、醤油の元となる「もろみ」を作り、半年以上寝かせます。
麹菌、酵母、乳酸菌などが働いて発酵が進み、さらに熟成されて醤油特有の色・味・香りが生まれます。
本醸造は温度管理などによってより安定した醤油を作るのに対して、
「天然醸造」は、より自然環境に任せた発酵で1年以上かけて作られます。
・麹菌 …… 消化促進・免疫力の向上・抗酸化作用
・乳酸菌 …… 腸内環境の改善・免疫機能の向上・アレルギー症状の緩和
・酵母菌 …… 疲労回復・腸内環境の改善・免疫力強化
などがあると言われています。

添加物を足さず時間をかけてじっくり発酵させた醤油は、これらの微生物が豊富に含まれていて、健康増進に役立ちます
混合
「混合」は、醤油の元となるもろみにアミノ酸や発酵調味料などを加えて攪拌し、熟成を早めた物です。
アミノ酸液が入っているので特有の旨みがあります。
混合醸造
「混合醸造」は、絞った醤油にアミノ酸液をブレンドさせています。
本醸造で作られた醤油にアミノ酸液や、酵素分解調味料などを加えて作ります。
アミノ酸液特有の旨みがあります。
国が定める添加物

国が定める添加物についても簡単に紹介しておきます。
- アミノ酸液 …… 大豆などのたんぱく質を塩酸で分解し、炭酸ナトリウムで中和したもの
- アミノ酸が液体に溶け込んでいて「うま味」を与える
- 短期間で大量に生産できるが、発酵によるものではなく科学的にタンパク質を分解しうま味成分を抽出したものなる
- 発酵分解調味液、発酵調味料 …… 大豆やトウモロコシなどを発酵・分解しうま味成分を得たもの
- 発酵時間を短くするために添加し、コストも抑えることができる
- 米発酵調味料 …… 風味の向上やまろやかさと甘味の追加、うま味の強化などに使われる
- 砂糖類 …… 味や風味の調整、発酵の促進、色やツヤを与える目的で使われる
- 糖類は、砂糖など天然のものもあるが、化学的や人工的に作られたものなどがある
- アルコール、焼酎、清酒 …… 保存性を高めたり、風味や香りを安定させて引き立てるためなどに使われる
- 醸造酢 …… ポン酢醤油などの製造や、保存性を高めるために使われる
- みりん、みりん風調味料 …… 甘みやまろやかさをつけるために使われる
- みりんは発酵調味料ですが、みりん風調味料は甘みを加えた人工的な甘味料

次は醤油の種類と合う料理をお伝えしますね
醤油の種類と料理との相性

スーパーに行くと色々な醤油が並んでいます。
基本の醤油はJAS規格では5種類です。
違いは、小麦や大豆の配分や、工程の違いによって5種類に分けられています。
- 白醤油は、最も色が薄い醤油で甘みがある
- 向いている料理 …… 炊き込みご飯、お吸い物、茶碗蒸しなど、色を付けたくない料理
- 淡口醤油は、西日本でおなじみの醤油で、発酵期間が短く濃口醤油より塩分が多いのが特徴
- 向いている料理 …… 煮物やお吸い物など、味、彩や出汁を活かしたい料理
- 濃口醤油は、全国で作られている一般的な醤油で、東日本でおなじみの醤油
- 向いている料理 …… つけ醤油から料理用まで、幅広く合う
- 再仕込醤油は、熟成期間が長い濃厚な醤油
- 向いている料理 …… 濃厚な味わいでお刺身に合う
- 溜まり醤油は、大豆の割合が多いのでうま味を凝縮させたような味わいが特徴
- 向いている料理 …… お刺身などのつけ醤油や照り焼きなど

醤油の特徴を理解することで、料理により深みを加えることができますね!
おすすめの醤油

ここまで、本物の醤油について解説してきました。
具体的な商品を知りたい方もいらっしゃると思いますので、ここからはおすすめの醤油をご紹介します。
結論から言うと、私がおすすめしている醤油は海の精株式会社の下記の醤油です。
原材料や作り方にとことんこだわった最高の醤油です。
こだわりの原材料
原材料は、有機大豆(国産)、有機小麦(国産)、食塩(海の精:伊豆大島産)です。
現在、国内で消費されている大豆や小麦のほとんどは輸入品であり、国産の有機大豆は非常に希少です。
塩は、同社が販売している天然塩「海の精あらしお」を使用。
この塩にはニガリ成分が豊富に含まれており、醤油にまろやかな塩味と深い旨味、甘味を加えます。
天然塩についてはこちらの記事にまとめています。
さらに、水は秩父山系の天然水を使用。標高1037mの山から湧き出る、1400年もの歳月をかけて自然にろ過された純粋な水が使われています。
こだわりの製法
杉桶を使い、昔ながらの製法で1年以上かけてじっくり発酵・熟成させる天然醸造法を用いているそうです。
大豆の比率を高め、水の量を抑えて濃厚なもろみを作り、美味しさを凝縮する「十水仕込み」により、旨味が強い醤油になっています。
さらに、しぼりたての生揚げ醤油を低温で加熱し、風味と香ばしい香りを保ったまま丁寧に仕上げられています。

ぜひチェックしてみてください!
まとめ:原材料と製造方法を確認!
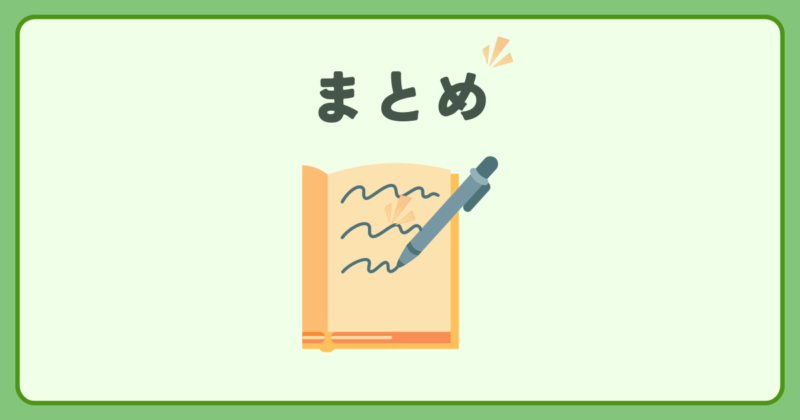
今回は、本物の醤油の見分け方を中心に、醤油の効果や種類と特徴についてまとめました。
- 本物の醤油は原材料が大豆・小麦・食塩
- 有機大豆・有機小麦・天然塩だとなお良い
- 時代や地域によっては米、大麦、裸麦、ハト麦で作られた無添加醤油がある
- 日本は加工食品も外食もほとんどが精製塩なため、意識して天然塩の醤油を選びたい
- 本物の醤油の製造方法は本醸造か天然醸造
- 農林水産省は、上記外の指定添加物が入っていても醤油と規定しているが、今回は無添加の醤油を本物と位置付ける
- 製法は「本醸造」「混合」「混合醸造」の3種類あるが無添加で伝統的な醤油は本醸造(天然醸造も含む)
- JAS規格では、白醤油・淡口醤油・濃口醤油・再仕込醤油・溜まり醤油の5種類
本物の醤油の見分け方は、名称の所に書いてある
原材料と製造方法で確認する。
製造方法が本醸造または天然醸造で、原材料が大豆・小麦・食塩であることに加え、有機大豆・有機小麦・天然塩を使用した醤油がベストです。
私がおすすめしている醤油は海の精株式会社の下記の醤油です。

これらのポイントを参考に、安心な上に美味しいい食生活を楽しんでくださいね!